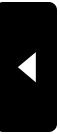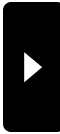2014年02月15日
ホワイト企業
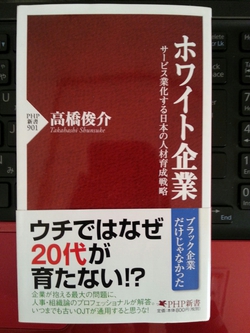 ホワイト企業
ホワイト企業高橋俊介
PHP新書901
編集者の意向か、珍しく世間受けをするタイトルだが、世間で言われている「ブラック企業」の単純な対義語としての「ホワイト企業」ではない。企業倫理や経営者の道徳観の問題と説いているわけではない
2次産業で成功を収めた日本の人材育成モデル(そもそも素地が外国とは違うが)を、そのまま3次産業の人材育成に適用するだけでは足りない
「働きやすさ」と「働きがい」、「クレーム対応」と「ポジティブフィードバック」、「背中を見る」と「可視化」、そして「求める人材」とそれを定着させるプログラムなどなど、分かりやすい実例と端的な解説
・・・これが理解できないと「今の若者は・・・」「オレの時代は・・・」と齟齬に気が付くこともなく組織が衰退していくのかも
しかし・・・イギリスのIIP(Investors in People)という人材育成企業の認定制度。こうしたプログラムを開発し制度化するとこも実利的だが、すかさずライセンス化するところが、まったく敵わない
モンドセレクションからISOまで、国際競技連盟からノーベル賞まで、ライセンスフィーとルールブックメーカー、これは圧倒的に欧州のもの。アメリカも2進法の世界でようやく足場を築いたところだ。これは3次産業より高次の4次産業と言えないか。金融で英米が強いのも3次産業的な範囲の問題ではなく、英語とドルの本家である所だ。ライセンスやルールブックは「国際競争力」以前の問題だ
世界を魅了する「おもてなし」や「和食」も、JISや柔道連盟のように日本が本家を守ることができるか。そういう意味でも、筆者が沖縄で取り組んでいるプログラムを嚆矢として、洗練させたうえで早くスタンダード化を目指さなければ
2014年02月02日
生物と無生物のあいだ
 生物と無生物のあいだ
生物と無生物のあいだ福岡伸一
講談社現代新書
STAP細胞制作記念
「生物と無生物のあいだ」というより、「動的平衡」という表現に代表される「生物」のメカニズムについて。「生物とは何か?」という内容
・互いに鏡写しの構造で、対となる情報の複製を容易にすることで、情報の安定性を担保するというDNAの2重らせん構造
・このDNAがもつ巧みな自己複製システムに基づいて「生命とは自己複製を行うシステム」と定義
・原子の大きさに比べて生物が一見不必要なほど「大きい」のは、原子のランダムな運動による「偏り」をなくし、「平均」として安定させるため母数(母体)を大きくとる必要があるため
・生命は「動的平衡の流れ」の中にある。イメージとして例示されている「砂の楼閣」が非常に分かりやすい。生命もエントロピーの法則に逆らえず絶えず「崩壊」しているが、一方で絶えず再構築が行われ増大するエントロピーを外部に排出している(つまり「代謝」という事でいいのか?)
・つまりは「秩序は守られるために絶え間なく壊されなければならない」と筆者。エントロピーの増大に対処する唯一の方法は耐久性の向上・強化ではなく、「(生命という)仕組み自体を流れの中に置くこと」これが「生物の内部に必然的に発生するエントロピーを排出する機能を担っている」
・そして個々の細胞が外部からタンパク質を取り込むこれまた巧みなシステム。これを説明する比喩もまた秀逸で、大きな風船に拳をあてて押し込む。押し込んだ手首の部分をくびれ取る(初めて聞いたが分かり安い表現)形で分離し小胞体となる、と。これで細胞は細胞膜をあける危険を避け、外部からタンパク質を取り込める。小胞体は細胞を横切り、細胞膜へと到達し、最初と逆の過程で外で排出される。DNAといい、細胞といいどうしてこんな見事な解決方法にたどり着いたのか・・・→では老化はなぜ起きる?
といった、内容が分かりやすい表現(その分図説は少ない)でアメリカでの研究生活や学会の裏表の人間臭い(ある意味下世話な)挿話とともに読者をひきつける
で、終章に近付くと
続きを読む
2014年01月24日
アメリカ型成功者の物語

アメリカ型成功者の物語
ゴールドラッシュとシリコンバレー
野口悠紀雄
この所、文庫本のアタリが続いている。テレ東ディレクター(高橋弘樹)のちくま文庫の「演出術」も良かった
この本は2005年に週刊新潮での連載を「ゴールドラッシュの超ビジネスモデル」として書籍化したものを2009年に左に改題し文庫化したもの
金鉱が見つかった農園主=ジョン・サッターの物語は単なる悲劇としてこぼれ話的に紹介されることが多いが、器具を買い占めたサム・ブラナン、ジーンズを製品化したリーバイ・ストラウス、駅馬車サービスを提供したウェルズとファーゴ、そしてCPとWPのBIG4、とりわけスタンフォード家の物語までしっかりつないでいるのが本書の特徴
それを現代のゴールドラッシュ=シリコンバレー黎明期からの物語とトレースさせている。簡単そうだがシリーズでありパラレルなストーリーを見事に整理して「物語」に仕立てている、さすが。「天才数学者はこう賭ける」の著者もこんな風に書きたかったに違いない。簡素にして十分な文
さて「社会が成功する条件」として「自由の天地に有能で意欲に満ちた者が集まり、互いに刺激を与えること」としているが・・・「沖縄はアジアの中心」と喧伝するよりも、その辺境性に注目してもらった方がいいかもしれない
マイノリティを受け入れる実績はある。新しいビジネスを始める「ヨソ者」も多く、少なからず成功者も出ている。ただそのスケールは限られる。足りないのは資本か、経営者か・・・あるいは別に島を飛び出しての成長を阻害する要因があるのか
2014年01月16日
日本人のための世界史入門
 日本人のための世界史入門
日本人のための世界史入門
小谷野 敦
新潮新書 506
ある意味すごい本。全編のうち、ほぼ半分がボヤキ
だから帯にあるようび「3000年を一冊で大づかみ」などできないし、もちろん入門書でもない
とはいえ、内容的には口語体で雑談を聞いているようで、話し相手が少ないであろう世界史好きがコラム的に読むには面白い
興味深いのは2013年2月20日に初版で、購入した本は同年4月30日の11刷になっていること
正直出版社もそんなに売れると思っていなかったに違いない。重刷も思い切ってかけ切れずに小出しにしたのか・・・このタイトルと帯の勝利。編集者は出世しただろう
2014年01月04日
スペイン史
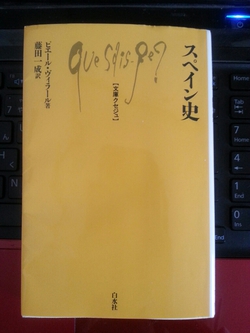
スペイン史
ピエール・ヴィラール 著
藤田一成 訳
白水社 文庫クセジュ731
スペイン通史はネットでもなかなか手ごろな本が見つからなかったが、ジュンク堂で発見。1992年第一刷、本書は09年の第九刷だがスペインが現体制になるまでが収録されている
まずスペインの哲学者・オルテガの著書から引用して、スペインには地理上の中心地を果たせる場所がなく「イベリア半島は無脊椎」としている。これは使い古された文句だそうだ
山脈が地域を分断している。ゆえにイベリア半島の歴史は「たいていの場合、中央部から表明される統合への意思と、やはり自発的な分立指向-それは地理的要因に根差している-との絶え間ない闘争だった」と第一章から切り込んでくる
中世~近世
永いモーロ人(ムーア人?)との戦い(781年間)の過程で各地域は自らがかちえた権利と戦いに対する誇り、そして近隣に対する不信感を抱くようになった
「スペインの実体が持つ新たな二面性~一方では自主独立路線~他方では超国家的な理想と情熱(カトリック信仰と守護)を求める傾向。この二つの傾向の間をスペイン人の意識は揺れ動いて容易に定まらない。これはいまだに続いている現象なのである」
「カスティリーヤ、レコンキスタ、そして中世などの精神―これらの精神は資本主義の萌芽に見られる事象に極度に逆行していた」
1580年にポルトガルとの統合(合同君主)が実現するも1640年にポルトガルは再度独立する(→ガリシア、イベリスモ)
「風土、人種、言語がカタルーニャを規定しているが、1750年から1830年の間、これらの要素はほとんど忘れられていた。~すなわち本当の問題は相違点にあるのではなく、特定の時期に特定の地域がこれらの相違点を再び意識するようになった理由の中になる。~かくしてカスティリーヤ人はカタルーニャ人に貪欲、金銭欲、威厳の欠如しか見いだせなかったし、カタルーニャ人はカスティリーヤ人に思い上がりと怠惰しか見出さなかった」
著者はフランス人だが、訳者によるとスペインでも名の知れたスペイン研究者だとか。スペインへの敬愛がにじみ出ているが、単なる「英雄史」にならずに宗教観や市民の感覚、生産基盤にまで言及した合理的な内容で理解しやすい。ただ、訳者が苦労したと言っているように、文章自体は詩的というか難解
訳者は神奈川外語大学の教授だがナバラ大学の修士課程を卒業し、数年間現地で研究生活を送っていたようでスペインへの敬愛の念を感じるいい翻訳だ
難しいが、164ページ、1050円(+税5%)では入門書として最適でお値打ち
続きを読む
2013年12月21日
天才数学者はこう賭ける
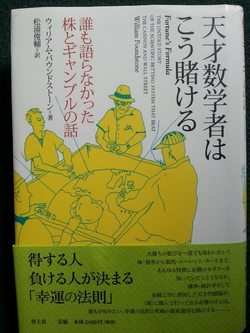 天才数学者はこう賭ける
天才数学者はこう賭ける誰も語らなかった株とギャンブルの話
ウィリアム・パウンドストーン
松浦俊輔 訳
青土社
情報工学の泰斗、クロード・シャノンや同じくベル研究所のジョン・ケリー二世といった数学者とエマニュエル・キンメルや”ロンギー”ツウィルマンといったギャングにギャンブル好きのエドガー・フーバー、そしてジャンクボンド王と言われたマイケル・ミルケンに連邦検事時代のルドルフ・ジュリアーニ、ポール・サミュエルソンとその弟子でLTCMのロバート・C・マートンの写真が扉についている
多彩だ。でも内容的には雑多というほかない。404ページの本文に16ページの原注。15名近い主要な人物にその関係がよく見えない関係者、無駄に入組んだ章立て・・・面白くなりかけたところで話が変わる
マニー・キンメルが駐車場から経営を多角化する過程で、スティーブ・ロスが経営に加わりワーナー・ブラザーズを買収しコングロマリットを変容させていく過程はたった2ページ・・・だいたい読者の想定が見えない
数学的なポイントとしては 続きを読む
2013年12月20日
成長から成熟へ
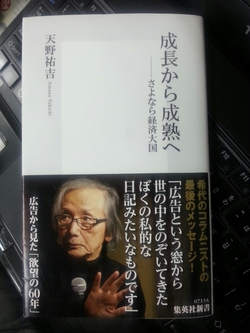
成長から成熟へ
―さよなら経済大国
天野祐吉 集英社新書
タイトルにあるような内容ではなく、むしろ帯にあるような「広告から見た欲望の60年」というべき内容
「日記みたいなものです」なんて断っているが立派な社会分析
広告は何も資本主義に特有の産物ではない~電球が1000時間で切れるように設計され~「欲望の廃品化」に一役買ってきた。といいう内容
→機能の廃品化(アップグレード)・品質の廃品化(計画的減耗)・欲望の廃品化(さまざまに古くなる)
この辺り、ヘンリー・フォードとGM、そしてその後のバッチ・エンジニアリング。そしてトーマス・エジソンとJPモルガンの関係といった産業史を思い起こすと、実はまだ決着がついていない部分(というか金融が加わり地平が広がっている)があるが、大筋理解できる
DDBの「そのうち消費者の無関心という大波が、私たちが作り出しているタワゴトの山に襲いかかる。その日こそ、私たちの最後の日だ~その日、私たちは私たちの市場で死ぬ。私たちの製品棚の上で。空虚な約束を記したメッセージの中で。物音もなく、すすり泣きもされず」というのは広告に対する意見広告だが、そのままメディア自体にもあてはまる
マクルーハンの「クールなメディア」ってのも分かるな
メディア間の競争や収益に目が向いているうちはいい。だけど、新しい価値・新しい伝え方をもったメディアが出てくると、いよいよマズいってのが本質的な問題だよな
率直に言ってヒントはありきたり(というか既に聞いた話)で、答えは見えてこないんだけど。DDBの意見広告は1969年なのに!
続きを読む
2013年12月05日
未知の国スペイン
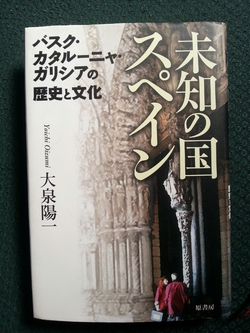 未知の国スペイン
未知の国スペインバスク・カタルーニャ・ガリシアの歴史と文化
大泉陽一 原書房
世界史に残る黄金時代を築きながら、なぜか日本では本が少ないスペイン
通史を探していたが、なかなか適当な本が見当たらない。でも、この本を読んで「スペイン」の通史が見当たらない理由が少しわかった
レコンキスタ以降のこの3地域だけを見ても、歴史が複雑
スペインとは何か?余計にわからなくなった。「民族」もやっぱり定義できない
バスクはともかく、カタルーニャもたびたび微妙な州民意識が紹介されているが、ガリシア語が「ほぼポルトガル語に近い」ってそんな複雑なの?
しかも著者は国立バジャドリード大学院を卒業し、そこでアジア研究センターの研究員ということで、歴史というよりも気候風土を知るエッセイとしてまとめられている感じ
これがまた、結構詳しくてスペインをよく知らない者には難しい。平易な文書だが、ネットであれこれと調べる必要がある。その段階で少しづつ、通史も見えてくるけど・・・
もっとも重要な収穫はフランコ体制下の全体主義の影響に関する記述。国粋主義に基づく歴史教育・・・多くの独裁国家で繰り返される背伸びをした尊大さ
巷のスペインのイメージとは違うが、実際にスペイン人を知らないのでどうなのか
レコンキスタは700年以上かかっている。グラナダの歴史はさらに複雑で素人にも分かりやすいスペイン通史はムリか・・・カスティリーヤの通史から探すか
2013年10月18日
不可能 不確定 不完全
 不可能 不確定 不完全
不可能 不確定 不完全ジェイムズ・D・スタイン
熊谷玲実 田沢恭子 松井信夫
ハイゼンベルグの不確定性原理(物理)、ゲーテルの不完全性定理(数学)、アローの不可能性定理(社会)という「三大できない」の証明を検証と背表紙にある通り
三大作図不可能問題の角の三等分問題にようにツール(目盛りのある定規)さえあれば、究極的に不完全が残るとは数学に限ってなさそうなものだが、ある
しかし、ネガティブさは微塵もない。いつもながら数学・物理学者一流のウイットに富んだもので、帯にあるように「決定不要の地平さえ包含する公理系を夢見る、数学の欲望」は尽きない
いまだに良くわからない「虚数解」すら使いこなしている数学/物理だから、究極的に不完全だろうが不確定だろうが、前に進むだろう
問題はどの方向に進むか・・・
重力を取り込むのは時間の問題。その後、有機物の世界をどこまで取り込めるか
一つの生命体の振る舞いは予想できないが、その集合体の振る舞いは予想できる
さらに生物界の個体から時間軸(歴史)に至るまで、等差数列よりも指数や対数の方が有用であることは明らかだ
この奇妙な一致から興味をそらすことはできない
近年の指数関数的な社会の変化は何か?今はカーブのどの辺りか?そしてx軸とy軸、いずれかに触れることはあるのか?それは何を意味するのか
また厄介なことに、生物界のチャートは視点を下げていくと、株のローソク足のようで、時間軸の取り方によってローソクの色が変化したり、移動平均が変わったりでトレンドの見極めすら惑わされる
そして、とりわけ厄介なのが、そのチャートのゼロ(絶滅)は見えるが、山を上りきったずっと後にしか、「あれが頂点だった」と気づきえないこと。ニセのトップか、真のトップか、これもまた観測で知ることは原理的に不可能
2013年10月14日
予想どおりに不合理
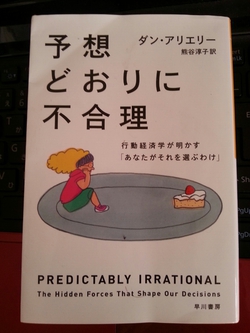 予想どおりに不合理
予想どおりに不合理ダン・アリエリー
訳:熊谷淳子 早川書房
行動経済学の基礎編
実験の手順などが細かく記されているのはいいが、聞き覚えのある話が多い・・・
ただ、やはりここでも文化の違いに注意は必要
どうやらアメリカでは先に注文した人とは「違う」ものを不本意ながら選び個性を演出する傾向があるようだが、日本なら逆だろう。本当は違うものを注文したくても「じゃ、私も・・・」という傾向だろう。もっとも、そうした感覚は薄れてきているが
そして、もっとも興味をひいた、「自制クレジットカード(項目別にあらかじめ設定した支出予定額を超えないように制限)」するカードは日本でこそありがたがられそうな仕組みだ
特に日本では銀行がカードの元締めとなっていることから、マーケティング的にも積立との連動や他のマイレージ等とのポイント交換で見栄えのいいビジネスができるかも
2013年10月01日
おどろきの中国
 おどろきの中国
おどろきの中国
橋爪大三郎・大澤真幸・宮台真司
講談社現代新書 900円
三名の著名な社会学者による鼎談
新書ながら378P+あとがきのボリューム。中国社会についての解説半分と論説半分といった感じ
原論とはいえ、帮(ほう)ですべてを説明しようとした小室直樹よりも具体的な議論になっていると思う
特に歴史の分岐点では帮とか言ってる場合じゃないのは、今に始まったことではないはずだ
例えば誰でも不思議に思う毛沢東の神格化ともいえる権力基盤の強固さと没した後の名誉の存続については、「疑似皇帝」という概念で説明している。なるほど
また文化大革命が結果的に近代化への扉を開けたというのも納得できる。歴史って
その他、「天」に選ばれたはずの皇帝が交代する(易姓革命)という理屈が歴史ものを読んでいてよく分からなかったが、「天命が尽きる」という考えがあれば、確かに矛盾もない
ただ「指導部は正しいというドグマ」はどうか?中国に行くとびっくりするぐらい公然と共産党への不満を口にしている(曰く「市民が意見を言う権利は当然にある。中国は独裁国家ではない。ただ、行動に移すとアウトだけどね」と言っていた)。
なにより消化不良なのは「驚きの中国」というタイトルありきの企画なのか、「そもそも国家なのか?」という帯までつけたためか、「中国はこんなにユニーク」という視点に引きずられすぎ。家族や民族が定義できないように、国家もそれぞれなのは社会学なら基本的な視点だろうに。俯瞰して括目させて欲しかった
2013年09月16日
金閣寺
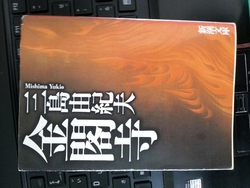 金閣寺
金閣寺三島由紀夫
新潮文庫 113刷
590円
三島の名を確立した普及の名作・・・
確かに素晴らしい作品。特に「文芸」とも言うべき技巧はまさに「鑑賞」に値する
強弱、緩急、動静、明暗、乾湿・・・一つの小説で見せびらかすような多彩な筆致。しかし全体に精密さと剛性感が通底し独特のしっとりとした重みを醸し出している
大学生のころ読んだときは、つまらないと思ったが、この文章の完成度の高さを今は理解できる
しかし・・・古い。実際に60年近く前に発表されただけに古いのは当然だが、そういう意味ではなく古さを感じる
何が古いのか?
「認識」と「行動」とか言ってるのが古いのか
スピード感あふれるクライマックスの後、「生きようと思う」とか言って終わる構成が古いのか
脚注を見返しながら読まなければいけないスタイルが古いのか
いずれにしても夏目漱石の作品は「時代」を感じても「古さ」は感じない
いや、古いというより、今の時代と合っていない、あるいは戦中~戦後という時代設定が古典としてみることを阻んでいるだけかもしれない
どのページを開いて読んでも、読み込んでしまう文章でありながら、もう一度読み返そうとは思わない。そんな感じ
2013年08月17日
社会を変えるには
 社会を変えるには
社会を変えるには
小熊英二
講談社現代新書128
新刊の新書なのに517Pという分厚さで1300円もする
だけど、それに値する内容と値段
タイトルにあるような社会運動論に表面的な目新しさはないが、それに至る知識の巨大さを感じさせられる。この上に法学や経済学は乗っかっているのだが・・・
算術から近代思想まで「西洋」の知の系譜がちゃんと一本に統合されている。なんだかすごくスッキリした
宗教や政治制度以前に、やっぱり基本的な価値観が違う。イデアと天国は方向性から違うが、スミスとマルクスは根は同じ。それが分からないとニュートンの錬金術をオカルトと決めつけてしまう・・・
つまり「真理」や「定理」、「永遠」を求めてやまない態度こそが、西洋の基本的な精神。現世に背をそむけるような思考様式を根本に持ち、それを突き詰める方向に常に収斂しながら、近代に入ると高度な文明と技術を併せ持っていたイスラム世界や中国すら抜き去り世界に拡散したというのが・・・
しかし、歴史は直線的に前進するのではなく反動や挫折もある。特にこれからは筆者が言うように単純に理論的に進める世の中ではない。単純な定理が成立しない非ユークリッド幾何学が現実の宇宙。集合のふるまいは予測できても、個のふるまいを予測しずらいのはモノも人間も同じ。もしかしたらパラレルワールドもあるかもしれないと科学者は真剣に考えている
これから社会を変えるのは何か?例えば素数にすごい秘密があるかもしれないが、今は西洋社会でもそんな研究をするのはラクではなかろう
意外と、これからは東洋哲学の出番かもしれない、がそれも彼らの理論を消化した上での話だろう
2013年07月17日
あなたの中の異常心理
岡田尊司
一見、ありがちな心理学の本だが、実在した人物や芸術作品を引用した具体的な解説で断然納得し解しやすい
ただ「誰もが異常心理を抱えている」という期待通りの小見出しからスタートし、ページが進むにつれ「あなたの中の異常心理」というタイトルから離れて行ってしまうのは少し残念。タイトルは編集者が後から付けたか?どちらにしても、手に取ってみたという事は成功。さすが幻冬舎
「異常心理=精神障害」「多くの異常心理の萌芽は幼い段階にあり、多くの人は成長とともに克服していく」とのまえがきからスタート
第一章は「本当は怖い完璧主義」
三島由紀夫やガンジーなどを例に挙げながら、その極端な行動とその源泉・原理を解説
二章は「あなたに潜む悪の快楽」
行為の自己目的化とそれに対する一般社会の生理的な反発。そして自己目的化する行為によって短絡的な快楽回路が出来上がり、無限にループ。他者の介在がなくなると歯止めを失いやすい
愛されないことが悪を生み、やがては「認められないことを嘆くより、自ら認められない存在になろう」という価値の逆転によって自己否定を肯定に変えてしまう
第三章「敵を作り出す心のメカニズム」
妄想分裂ポジション=自分の意思を邪魔するものはすべて敵。抑うつポジション=不快の原因は自分にあるのではないかと考える。抑うつポジションが発達するためには全体的な視点を持つことが求められ、その達成には十分な共感の下で自らの非に向き合う必要がある
支配感・征服感・軽蔑という自己防衛。支配欲こそは人間の根源的な衝動なのか?そして支配は中毒になる→スタンフォード大の監獄実験(ミルグラム実験)。社会的役割が個人を超えて、その人の行動を支配する→非個人化。看守役は看守らしく、囚人役は囚人らしく古○用になってくる
ラべリングは問題解決を困難にする心理プロセス。先入観の産物
七章「罪悪感と自己否定の奈落」
問題に行き当たるとき、ユングは正面から向き合うようにしていた。問題の回避は目先の破たんを避けるメリットはあるが、本当の回復を遅らせる、と
2013年07月07日
ニュートン2013年8月号
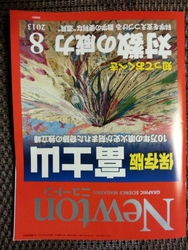 経済が動いているのに読みたい本がない
経済が動いているのに読みたい本がない「よく分かる」系の本はともかく、なんだか結論ありきの本ばかりで経済書というより、政治書のようだ
もちろん、いい本もあるんだろうがネットの解説で自分が中途半端に知ったような気分になっているからか、お金を出して買う気になれない。こんな人間が増えてくるから、より刺激的な内容や見出しの本ばかりになり、余計に読みたい本がいというインフレーションになっているのかもしれない
だいたいブックオフに行けば、今見るとなんでこれが?と思うような本こそ売れてたりしているのが分かる
情報過多の時代。でも、どんな時でも先端科学と土台となる数学は魅力的
今月号は富士山は・・・まあ、集大成
それより「対数」という数学でも地味めなテーマが面白い。対数⇔指数は経済学では微積分と並んで必須。というより「その倍」という計算式が自然界のみならず、人間の感覚(星の等級づけ)に当てはまり、それが人間の心理に影響を与えているということだ
今号は指数ではなく対数に注目している。指数に比べて用途が分かりくいが、指数が「答えはいくつ?」なのに対し、対数は「答えに必要なものは?」という感じ。つまり政策決定はコチラだ
となると、経済政策の成否はファンダメンタルの大きな変化を除けば、人間(市場参加者)の感受性と出動可能な政策の量との兼ね合いであることが分かる・・・
「雲」や「窓」「カイリ線」・・・チャート化されている株価が一番わかりやすいが、一人の人間の行動を予測するのは難しくても、その人間が集まると行動が数式に近づき読みやすくなるという矛盾もまた面白い
(逆に、市場における大型プレイヤーや政治のリーダーなどは独立した力を持っている)
しかし、教育再生というなら、144ページ1000円のこの本が200円ぐらいで買えるようにしてくれないかな。科学や数学に興味がない人は「図書館に置いてあるじゃないか」と言うだろうけど、ほんと分かってない。ベットで読めなきゃ数学や科学の面白さなんて染みてこない
2013年06月30日
暴走する資本主義
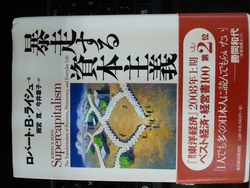 『暴走する資本主義』
『暴走する資本主義』Supercapitalism
ロバート・B・ライシュ
2007年に米国で出版、翌2008年に日本語版が東洋経済出版より。久しぶりに読むと経済書とは別の面白さが見えてきた。本も発酵するのか?
暴走する資本主義というタイトルは、社会全体への責任と調和が企業経営者に求められ実行していた社会資本主義的な時代(米国では60~70年代。著者は「疑似黄金時代」と呼んでいる)は過去のものとなり「最良の取引(つまり「より安く」「より多く」)」を求めて投資家・経営者・消費者が選択を繰り返す現状をさしている。つまり資本主義本来の姿。ただ、インターネットや航空機、法整備などによって「取引き」の範囲が国境を越えて地球規模という、し烈さは過去にないもので、それが「Supercapitalism」
この辺りまでは前作の「勝者の代償」をなぞるような感じ
その結果、格差が広がり、機会の平等さえ失われつつあることを著者は憂慮している。そして、これは企業経営者にその責任があるわけでもなく、投資家でもある市民、つまり一人一人がより大きなリターンを求め、より安い製品を求めている結果であるとしている。そして経営者、投資家そして市民も「最良の取引」を求めるのは当然であり、誰も責められないとしている。そして「だから政策が必要なんだ」としている
そして面白いのはここからだ
その政策とは「強調されるべき(そしてもっとも基本的な)最後の真実は、企業は人ではないということである。企業は法的擬制であり、契約書の束以外の何物でもない(P297)」と論破している。全くその通りだ。しかし「法人」は人じゃないが、権利を持っているし税金も納めている、だから「企業は民主主義のプロセスに参加する資格を与えられるべきだと思い込んでいる」としている
そして・・・
法人税は廃止されるべき。そもそもそれは間接的に消費者や株主、従業員が払っている。そして非効率(配当は法人税所得から控除されないのに債務の支払いは金利は控除される。それでは資金調達は直接金融ではなく銀行からの借り入れとなり、配当よりも内部留保を助長する。その内部留保は他企業の買収や株式の消化に充てられている。それが配当に回し、投資家の手にゆだねた方が市場効率は上がるはずだ、としているP298)。さらに不公平(内部留保に対して法人税が課せられるが、その税率は低所得の株主に配当された場合に彼らが個人所得に対して支払うことになる税率より概して高い。反対に高所得の株主に波頭される利益にかかる税率はその個人所得に通常課せられる税率‐累進性が前提。つまり法人税率は中間にあるということ‐より低い)
よって法人税を廃止し、すべての法人所得を株主の個人所得と同じように扱えばこの変則的な状況も是正される、としている(P299)
そして、企業が刑事責任を問われることも擬人化を助長するとしてやめるべき、企業には意思がないと説いている
また国家は米国企業の競争力強化を支援するよりも、米国人の競争力を強化すべきだと主張している
言っていることはわかるが、それで社会の調和を取り戻すことに成功するかはは私にはわからない。「法人税」は何かその必要があるから創設され、今日まであるのではないか?例えば、営業利益を配当に回した場合、投資先としてはかなり魅力的となり、海外からの投資が増え、結局配当という形で資本が海外に流出してしまう、など
もしかしたら単に利権を持つ人たちの都合で「銀行」にお金を通すための仕組みとしてあるだけかもしれないけど・・・
また米国企業より米国人の競争力強化というのももっともな話であるが、では支援を得て競争力を持った個人が海外企業に就職し、海外に住み、そこで所得税を払うこともあるのではないか?
(→ヘンリー・ジョージ『シンポと貧困』)
しかし 続きを読む
2013年06月08日
勝者の代償
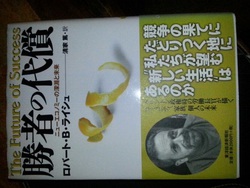
勝者の代償
ロバート・B・ライシュ
クリントン政権の労働長官が退官後の2002年に出版。原題「The Future of Success」を「Past of Future」で振り返る。この本から10年余り・・・
まず、「別の社会」と思われた日本も構造的な部分でやはりアメリカを追従している―
A.スピード
まず技術的には当時著者が想定してなかったであろうスマートフォンの登場もあり、人と人が「常時接続」となった。海外の路上にいても手元にEメールが届き、返信できるようになった。
サービス面では日本的な高品質に加え宅配などでは「24時間」と「配達時間の短縮」が重要項目になっている
消費においても「限定」で陳腐化を防ぐというマーケティングが一般化した。従来「限定」とは周年の記念モデルなどが中心だったが、今では耳目を引き付けるための表層的な装飾といった感じだ
世界的には金融界に「高速取引」というスピード自体が利益に直結するという「取引き」まで現れた
B.不安定さ
10年前に誰が今のソニーやパナソニックの苦境を予言したか。以前企業の盛衰は10年単位だったのが、年単位になった感じだ。世の移ろいは宿命だが、スピードが人を不安定感を増長し人を不安にさせる。著者が「干し草」に例えているのは個人の貯蓄だが、日本では貯蓄に回される余裕もない。しかし企業の内部留保は266兆円にも上るという
これが労働者に分配されれれば消費は刺激され、生産性を上げる画期的な研究の成果につながればパイを増大させるが、・・・政権再交代から半年余り。政府が旗を振っても(というより笛を吹いてもという状態か)まだ具体的な動きにつながっていない。ボーナス満額支給などは内部留保の切り崩しではなく、円安還元という方が正確
C.サービスの外注
ホームパーティーの文化がない日本では、誕生会のアウトソーシングこそない(あるかもしれないが一般的ではない)が、介護などはプロに頼るのが普通になった。食事は冷凍、中食などの形でアウトソーシングされている。シーミーの重箱を「買ってくる」のは、この10年ですっかり一般的になったのはチラシで明らか。(著者曰く友人に代わる)良きアドバイザーである「コーチング」も沖縄にも登場しているが、まだまだ
D.階層化
「ママカースト」「スクールカースト」という言葉が東京ではあるそうだ。沖縄でも不動産のマス媒体広告に「校区」が大書きされるようになったのはここ5年ぐらいか。ただ、まだ沖縄では所得による階層は、(特に富裕層側からの)意識はともかく、アメリカのように(地域や学校など)は目に見えるものはほとんどない
日本でも「経営者」は一般労働者と比較できないほどの「高給取り」であることが珍しくなくなった
サービス面でもネット上の「タダ」やLCCに代表される「低価格」が一般化したが「有料」は特別なサービスがあるし、「プレミア」戦略も低価格が広がるほどに企業の力が入っている感じ
もっとも、うまくやれば「ホットケーキ」を2000円で提供する飲食店もあるなど、今日の「プレミア」は従来の「上等」「高級」とは明らかに違う概念だ
という辺りが、出版から10年後の現状かな
続きを読む
2013年05月19日
地図で読む 日本の古代史
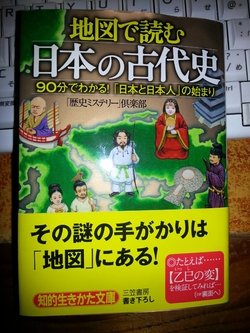 地図で読む
地図で読む日本の古代史
三笠書房 知的生き方文庫
ありそうで意外と見つからない古代日本についての本・・・古代と言っても邪馬台国は3世紀。蝦夷、勇人の征討は8世紀まで行われていたとなると、大昔という感じでもない
しかし、この間のことは日本史の教科書では触れられていないだけに新鮮
しかし著者の「歴史ミステリー」倶楽部って何だ?委員収入やマスコミ出演料など副収入が見込めない史学の研究者が連名でアルバイト?
ちなみに「地図」はあったほうがわかりやすいのは間違いが無いが、理解が一気に進むというほどではない
人物の「氏」や「姓」など基礎的なことの説明は無い。いまや歴史の本はマニアしか読まないという前提なのか・・・
優れた文化を持ち込んだ渡来人や列島内にも異民族を抱えていた時代には残念ながら前掲の渋谷氏が言うほど日本は特別ではない。権力争いによる政変や暗殺は度々あったようだ
その後の兵部の衰退は単なる「刀狩り」だったのか・・・
それよりも鎖国令以前も海外とのつながりが、遣隋使や白村江ぐらいしかない、希薄なものかと思っていたら、以外にも頻繁なやり取り
中国や高句麗あたりの古文書が発見されると歴史観が変わるほどの朝鮮や中国との「外交史」が明らかになるかもしれない
2013年05月05日
日本史集中講義
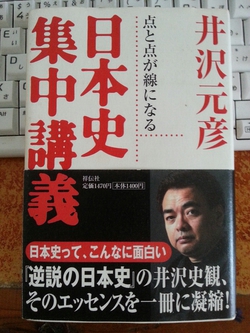 日本史集中講義
日本史集中講義井沢元彦
帯に「井沢史観」とあるが、西洋史などを読んでいるとむしろ当たり前の見方に思える
「歴史」とは「社会史」。筆者が主張するように年号と出来事を覚えるだけでの暗記では面白くない。だからと言って英雄伝では読み物で終わる
点が単なる結節点なのか、変節点なのか、断絶なのか・・・社会は人間が偶然に、あるいは過去から学び発明するもの
しかし「言霊」というのは面白い。琉球でもオギヤカが「祟り」を持ち出している。クーデターで王権をとったのだから、そのあたりは周到な「人事」で対応しそうなものなのに
また、第二尚氏への王統の遷移も「禅譲」ということになっている。もちろん、中国向きにはそんな話は信じてもらえないと分かっていたのか、親子関係と報告したようだ
「言霊」「国譲り」・・・これは日本語系統を使うものたちの共通の文化特性なのか、それとも文化の熟度の問題なのか(琉球の国譲りは1470年)、あるいは島国に見られる文化だったりするのか・・・
日本ではなぜか古代の研究が進んでいないように思える。チブサン古墳などの解明が進めば、農耕により人が土地に縛られる前のダイナミックな人の流れが見えてくると思うのだが
2013年05月04日
高等弁務官
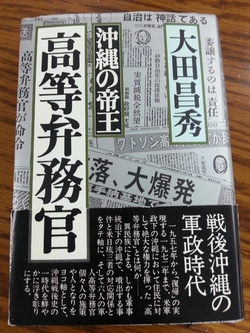 沖縄の帝王 高等弁務官
沖縄の帝王 高等弁務官大田昌秀
久米書房 1984年 4800円
4.28関連でライブラリー映像を引っ張り出すも、キャプションが不足しているため、この本を引っ張り出す
やはり研究者としての大田昌秀はさすがだ。アメリカに行って1次資料からあたり、463ページに小さな文字でギッシリと「詰め込んで」いる
これで4800円・・・一体誰が買い、読むというのか?と、思ったときに弁務官のインタビューを見ていて、どこか理解できない部分が符合した-「沖縄はサンフランシスコ講和条約で切り離されたのではなくて、大和と切り離せると見たから講和条約の3条がある」
西洋の歴史は単なる英雄伝ではない。「統治」や「契約」等々こちらから見ると複雑な概念の下の「力」の変遷と支配の在り方が記されている。それがわかるとカーの「琉球の歴史」の内容とそれらを下敷きとした彼らが描こうとした「線」が見えてくる・・・歴史を「点」で見る傾向があるこちら側とは違う
しかも文字や映像にして「残す」ということの重要性を先に知っているものだから、アメリカに当てた歓迎の文書や、映像では高等弁務官が主席と仲良くやっている所や、琉球政府幹部達を前にリラックスしたバックショットなど当時の映画さながらに演出された映像が残されている
・・・これを、本を読まない、歴史を知らない、傀儡という言葉を知らない人が見るとどうか?50年後には文書と映像しか残っていないかもしれない。この大田の本にしろ「読んだ」という人にお目にかかったことが無い。今、本屋の主力「商品」はハウツーや「なるほど」とひざをたたきやすいエッセンス本。注釈だらけの本なんてこの先大学生でも読まないのかも
しかし歴代弁務官の映像は、率直に「カッコイイ!」と思えるもの。キャプションのカチンコを持って出てくるコリスポンデントの助手(そこらにいた兵士かも?)などを見ると、非常にリラックスしており、アングルが「お決まり」なところを見ると「指定」のアングルがカメラマンには教授されているのだろう。みな、マッカーサーばりに周囲を一瞥してタラップを降り、勝者の余裕で笑顔を振りまき、部下の前では威厳を正す、というパターン
ただ、検閲があり米軍の意向に沿わない報道が制限されていた中でも、残っている映像はある 続きを読む