2017年08月23日
澁澤敬三著作集 渋沢三代
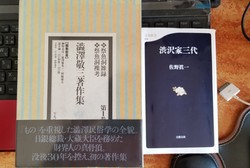 澁澤敬三著作集 第1巻
澁澤敬三著作集 第1巻 渋沢家三代 佐野眞一著
驚くから探して読んでみろと言われ、「じのーんBOOKs」で一冊残っていた著作集を購入。7千円。一通り読まれた本のようだが、丁寧な扱いで読む分に程度の問題はなし
で読んで確かに驚く。まさに博識で視野も深く広くかつ平明簡易な文章。平成10年発行の佐野氏の本の方がよっぽど大時代的な感じ
沖縄はとかくキャラが立つて売れるのといろいろ書きやすい環境もあって、たかだか数年の「個人的な経験」で汎論的な本まで書いてしまう人もいるが、自らの残念さだけを体現するものがほとんど。(佐野氏の著書は結構な取材で、沖縄の人間も絶句orうなってしまうが) 。ともかく情報化社会と言いつつも、「見たいものだけを見て」情報に流されるだけという中で、大正・昭和初期に情報を掘り下げ多くの比較対象を持っていたとは、やはり「エリート」はいるのだと改めて思い知らされる
またイタリア旅行記に見られるように、西洋文化に深い敬意と理解を示しながらも、西洋への対抗から創作された規範ではなく、土着の「生活」への愛着とそれを裏付ける自国文化への自信はどこから来るのかと思っていたところに追加情報で「渋沢三代」へ。これは傍線付きで、それがまた的確だから字句は古いが非常に読みやすかった(笑)
なるほど澁澤栄一は藩閥政治家とは出自から経歴、思想までだいぶ違うようだ。金銭に対しては潔癖な面もあるが、一方で下衆な部分もある。これを二面性という人もいるかもしれないが、一人の人間としては何の矛盾もない。栄一、篤二、敬三と周囲からは理解に苦しむあるいは直接迷惑をこうむる場面もあるが、それぞれに筋が通っている。それだから筆も取りたくなるし読んで面白い
面白いという俗な表現が本当にピッタリ。「人間」を描き切った小説のような「渋沢三代」には何とも言えない漫然とした読後感がある
たった数日の滞在で沖縄の文化の基底と独創的な部分とを見切った渋沢敬三
屋良朝苗は南方同胞援護会の初代会長を直談判でお願いしたというが、それは元日銀総裁・大蔵大臣という肩書なのか、南東見聞録によるものなのか、いずれにしろ「にこやかに没落」中の澁澤にちゃんと目を付けたのはさすが
また著作集を読んでいると、民俗学が大学で歴史学系ではなく社会学系に分類されていたのもよく分かった。人間というのは社会に生まれ、規定されながら育ち、く社会を残して消えていく存在なんだと思う
Posted by 比嘉俊次 at 11:34│Comments(0)
│社会












