2013年06月30日
暴走する資本主義
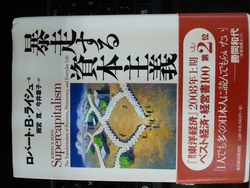 『暴走する資本主義』
『暴走する資本主義』Supercapitalism
ロバート・B・ライシュ
2007年に米国で出版、翌2008年に日本語版が東洋経済出版より。久しぶりに読むと経済書とは別の面白さが見えてきた。本も発酵するのか?
暴走する資本主義というタイトルは、社会全体への責任と調和が企業経営者に求められ実行していた社会資本主義的な時代(米国では60~70年代。著者は「疑似黄金時代」と呼んでいる)は過去のものとなり「最良の取引(つまり「より安く」「より多く」)」を求めて投資家・経営者・消費者が選択を繰り返す現状をさしている。つまり資本主義本来の姿。ただ、インターネットや航空機、法整備などによって「取引き」の範囲が国境を越えて地球規模という、し烈さは過去にないもので、それが「Supercapitalism」
この辺りまでは前作の「勝者の代償」をなぞるような感じ
その結果、格差が広がり、機会の平等さえ失われつつあることを著者は憂慮している。そして、これは企業経営者にその責任があるわけでもなく、投資家でもある市民、つまり一人一人がより大きなリターンを求め、より安い製品を求めている結果であるとしている。そして経営者、投資家そして市民も「最良の取引」を求めるのは当然であり、誰も責められないとしている。そして「だから政策が必要なんだ」としている
そして面白いのはここからだ
その政策とは「強調されるべき(そしてもっとも基本的な)最後の真実は、企業は人ではないということである。企業は法的擬制であり、契約書の束以外の何物でもない(P297)」と論破している。全くその通りだ。しかし「法人」は人じゃないが、権利を持っているし税金も納めている、だから「企業は民主主義のプロセスに参加する資格を与えられるべきだと思い込んでいる」としている
そして・・・
法人税は廃止されるべき。そもそもそれは間接的に消費者や株主、従業員が払っている。そして非効率(配当は法人税所得から控除されないのに債務の支払いは金利は控除される。それでは資金調達は直接金融ではなく銀行からの借り入れとなり、配当よりも内部留保を助長する。その内部留保は他企業の買収や株式の消化に充てられている。それが配当に回し、投資家の手にゆだねた方が市場効率は上がるはずだ、としているP298)。さらに不公平(内部留保に対して法人税が課せられるが、その税率は低所得の株主に配当された場合に彼らが個人所得に対して支払うことになる税率より概して高い。反対に高所得の株主に波頭される利益にかかる税率はその個人所得に通常課せられる税率‐累進性が前提。つまり法人税率は中間にあるということ‐より低い)
よって法人税を廃止し、すべての法人所得を株主の個人所得と同じように扱えばこの変則的な状況も是正される、としている(P299)
そして、企業が刑事責任を問われることも擬人化を助長するとしてやめるべき、企業には意思がないと説いている
また国家は米国企業の競争力強化を支援するよりも、米国人の競争力を強化すべきだと主張している
言っていることはわかるが、それで社会の調和を取り戻すことに成功するかはは私にはわからない。「法人税」は何かその必要があるから創設され、今日まであるのではないか?例えば、営業利益を配当に回した場合、投資先としてはかなり魅力的となり、海外からの投資が増え、結局配当という形で資本が海外に流出してしまう、など
もしかしたら単に利権を持つ人たちの都合で「銀行」にお金を通すための仕組みとしてあるだけかもしれないけど・・・
また米国企業より米国人の競争力強化というのももっともな話であるが、では支援を得て競争力を持った個人が海外企業に就職し、海外に住み、そこで所得税を払うこともあるのではないか?
(→ヘンリー・ジョージ『シンポと貧困』)
しかし
大学で民法を勉強するときにあれだけ「法人」という概念に違和感があったのに、今では当たり前に社会の参加者として認めている自分に気づいたのが一番の収穫かも。もしかすると明治以前、日本にも法人はなかったのかもしれないな。「越後屋」は税金を納めていたのか、それともオーナーや番頭だけが税を払っていたのか・・・
そもそも、この文脈だと「法人」と翻訳した方がよさそうなのに、「企業」と訳している。原著がそうなのか?法人は英語で「juridical person」とある。法人はこれの単なる直訳?
もしそうだとすると日本でも「法人」が誕生して100年余り。今や日本の法人も「契約の束」から立体となって立ち上がり、影さえ持ち始めているといえるかもしれない。米国ほど資本主義は先鋭化していないが、確実に後を追っている。株式への優遇でタンス預金を市場へという政策(401kやNISA)が浸透すれば、社会の調和を重視する日本でも様相が変わってくるだろうか
著者は言う、「政治的な権利を持つのは生身の人間のみであるべきなのだ(P298)」「企業は民主主義において権利も責任も持つべきではない。それは生身の人間だけが持つべきなのだ(P300)」と述べている・・・フィリップ・K・ディックの世界ではないか?「法人はタックスヘイブンの夢を見るか?」あるいは単に法人や資本が絶対君主として復活しただけの「マイノリティーリポート」に過ぎないのか
そもそも、この文脈だと「法人」と翻訳した方がよさそうなのに、「企業」と訳している。原著がそうなのか?法人は英語で「juridical person」とある。法人はこれの単なる直訳?
もしそうだとすると日本でも「法人」が誕生して100年余り。今や日本の法人も「契約の束」から立体となって立ち上がり、影さえ持ち始めているといえるかもしれない。米国ほど資本主義は先鋭化していないが、確実に後を追っている。株式への優遇でタンス預金を市場へという政策(401kやNISA)が浸透すれば、社会の調和を重視する日本でも様相が変わってくるだろうか
著者は言う、「政治的な権利を持つのは生身の人間のみであるべきなのだ(P298)」「企業は民主主義において権利も責任も持つべきではない。それは生身の人間だけが持つべきなのだ(P300)」と述べている・・・フィリップ・K・ディックの世界ではないか?「法人はタックスヘイブンの夢を見るか?」あるいは単に法人や資本が絶対君主として復活しただけの「マイノリティーリポート」に過ぎないのか
Posted by 比嘉俊次 at 00:40│Comments(1)
│社会
この記事へのコメント
どういうわけか、ライシュの本は写真がタテになってくれない・・・回転させても横になる。それともティーダのシステム変更か?
Posted by 比嘉俊次 at 2013年06月30日 09:34
at 2013年06月30日 09:34
 at 2013年06月30日 09:34
at 2013年06月30日 09:34










