2013年06月08日
勝者の代償
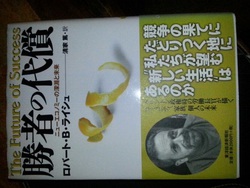
勝者の代償
ロバート・B・ライシュ
クリントン政権の労働長官が退官後の2002年に出版。原題「The Future of Success」を「Past of Future」で振り返る。この本から10年余り・・・
まず、「別の社会」と思われた日本も構造的な部分でやはりアメリカを追従している―
A.スピード
まず技術的には当時著者が想定してなかったであろうスマートフォンの登場もあり、人と人が「常時接続」となった。海外の路上にいても手元にEメールが届き、返信できるようになった。
サービス面では日本的な高品質に加え宅配などでは「24時間」と「配達時間の短縮」が重要項目になっている
消費においても「限定」で陳腐化を防ぐというマーケティングが一般化した。従来「限定」とは周年の記念モデルなどが中心だったが、今では耳目を引き付けるための表層的な装飾といった感じだ
世界的には金融界に「高速取引」というスピード自体が利益に直結するという「取引き」まで現れた
B.不安定さ
10年前に誰が今のソニーやパナソニックの苦境を予言したか。以前企業の盛衰は10年単位だったのが、年単位になった感じだ。世の移ろいは宿命だが、スピードが人を不安定感を増長し人を不安にさせる。著者が「干し草」に例えているのは個人の貯蓄だが、日本では貯蓄に回される余裕もない。しかし企業の内部留保は266兆円にも上るという
これが労働者に分配されれれば消費は刺激され、生産性を上げる画期的な研究の成果につながればパイを増大させるが、・・・政権再交代から半年余り。政府が旗を振っても(というより笛を吹いてもという状態か)まだ具体的な動きにつながっていない。ボーナス満額支給などは内部留保の切り崩しではなく、円安還元という方が正確
C.サービスの外注
ホームパーティーの文化がない日本では、誕生会のアウトソーシングこそない(あるかもしれないが一般的ではない)が、介護などはプロに頼るのが普通になった。食事は冷凍、中食などの形でアウトソーシングされている。シーミーの重箱を「買ってくる」のは、この10年ですっかり一般的になったのはチラシで明らか。(著者曰く友人に代わる)良きアドバイザーである「コーチング」も沖縄にも登場しているが、まだまだ
D.階層化
「ママカースト」「スクールカースト」という言葉が東京ではあるそうだ。沖縄でも不動産のマス媒体広告に「校区」が大書きされるようになったのはここ5年ぐらいか。ただ、まだ沖縄では所得による階層は、(特に富裕層側からの)意識はともかく、アメリカのように(地域や学校など)は目に見えるものはほとんどない
日本でも「経営者」は一般労働者と比較できないほどの「高給取り」であることが珍しくなくなった
サービス面でもネット上の「タダ」やLCCに代表される「低価格」が一般化したが「有料」は特別なサービスがあるし、「プレミア」戦略も低価格が広がるほどに企業の力が入っている感じ
もっとも、うまくやれば「ホットケーキ」を2000円で提供する飲食店もあるなど、今日の「プレミア」は従来の「上等」「高級」とは明らかに違う概念だ
という辺りが、出版から10年後の現状かな
で、肝心なのは「この世界の苦労と忙しさは何ためだろう。貪欲と野望の先にあるものは何だろうか」というアダム・スミスへの回答だが―これが1759年という今から見れば「スロー」な世界の言葉というのが失笑だが―この10年「景気回復」「規制緩和」「構造改革」などさまざまな言葉があったが、小泉政権時に雇用面で流動化が促された以外に大きな社会的な選択はなされていない。流動化といっても、割を食ったのは80年代生まれ以降の若い世代だ
ただ、何となく社会に「不安」や「不満」は確実に蓄積されている。2008年の政権交代はその表出だった(かなり大きな社会的選択があったのを忘れていた)が、「不発」に終わった。後講釈は誰でもできるが、今にして思えば民主党は「新しさ(新機軸・新発想などのコペルニクス的な)」を期待されていたのに、従来の延長線上でモノを考えていたのが不発の原因かな
著者が「もたらす結果になんら決定が下されないままに、一つの発展が次の発展の口火を切っているように見える」と言っている通り(これはいわば当たり前だが、スピードが速すぎるという意味)、変化を認識する前に次の変化が起きてしまっている。アップルのCEOは「税金逃れ」の批判に「アメリカの税制が時代に対応してない」とも
ただ、面白い現象もある。従来「技術革新」=「生産性の向上」だったが、最近はそうでもない。新しいウインドウズ8では、このブログの写真を縦に表示することは1時間かかってもできなかった。クラウドなど、グーグルなどがすでに提供しているサービスを今頃出してきて(だがワード・エクセルなどはしっかりと万単位で有料)パスワードの入力を求めてくる煩わしさ。その一方でエクセルの日本語表示の不安定さはバージョンをいくら重ねても解消されない。今までのドキュメントの蓄積を考えると今更乗り換えもでず、高くてバグが解消されないソフトを買い続ける他ないなんて・・・
スマートフォンだって、2年で陳腐化するというのに、買い替えた後に設定などを復元するのにたっぷり12時間以上かかる。おまけにウィルス感染の心配も出てきた。「便利」といっているが、果たしてこれは「生産的」と言えるのか?
「発展」に副作用はつきもの。車の登場は交通事故者を生み出した。でも一連の「デジタルの副作用」はうまく説明できないが、質が違うように思う。従来の「副作用」が「車の運動エネルギーが凶器にもなる」というような表裏一体であったのに対し、小さいがあらゆる面に影響を及ぼす波紋型。スマホは便利だが、生活の隅々まで仕事の侵入を許し、セキュリティで人を不安にさせ、設定で時間を食う・・・面倒だ
一方で興味深いのは選択≒自由がないアップルのアイフォーンがもっともブランド力があるスマートフォンという現象。当初は機能面で圧倒したが、今はそうでもない。むしろ「ない」機能がいくつもある。でもファンにはそんなことは関係ない。デジタル商品も、また商品でもある
結局、何が変わろうが、人間の「より良く」「損はしたくない」という合理性と、「差別化したい」「よく見られたい」という虚栄心の織り目は変わらない。ただ織り込んでいる素材が速乾性でやたら伸縮性があるけど、なんか縫製が悪いのか肩や腰のあたりがフィットせずしっくりこない・・・そんな感じかな
ただ、何となく社会に「不安」や「不満」は確実に蓄積されている。2008年の政権交代はその表出だった(かなり大きな社会的選択があったのを忘れていた)が、「不発」に終わった。後講釈は誰でもできるが、今にして思えば民主党は「新しさ(新機軸・新発想などのコペルニクス的な)」を期待されていたのに、従来の延長線上でモノを考えていたのが不発の原因かな
著者が「もたらす結果になんら決定が下されないままに、一つの発展が次の発展の口火を切っているように見える」と言っている通り(これはいわば当たり前だが、スピードが速すぎるという意味)、変化を認識する前に次の変化が起きてしまっている。アップルのCEOは「税金逃れ」の批判に「アメリカの税制が時代に対応してない」とも
ただ、面白い現象もある。従来「技術革新」=「生産性の向上」だったが、最近はそうでもない。新しいウインドウズ8では、このブログの写真を縦に表示することは1時間かかってもできなかった。クラウドなど、グーグルなどがすでに提供しているサービスを今頃出してきて(だがワード・エクセルなどはしっかりと万単位で有料)パスワードの入力を求めてくる煩わしさ。その一方でエクセルの日本語表示の不安定さはバージョンをいくら重ねても解消されない。今までのドキュメントの蓄積を考えると今更乗り換えもでず、高くてバグが解消されないソフトを買い続ける他ないなんて・・・
スマートフォンだって、2年で陳腐化するというのに、買い替えた後に設定などを復元するのにたっぷり12時間以上かかる。おまけにウィルス感染の心配も出てきた。「便利」といっているが、果たしてこれは「生産的」と言えるのか?
「発展」に副作用はつきもの。車の登場は交通事故者を生み出した。でも一連の「デジタルの副作用」はうまく説明できないが、質が違うように思う。従来の「副作用」が「車の運動エネルギーが凶器にもなる」というような表裏一体であったのに対し、小さいがあらゆる面に影響を及ぼす波紋型。スマホは便利だが、生活の隅々まで仕事の侵入を許し、セキュリティで人を不安にさせ、設定で時間を食う・・・面倒だ
一方で興味深いのは選択≒自由がないアップルのアイフォーンがもっともブランド力があるスマートフォンという現象。当初は機能面で圧倒したが、今はそうでもない。むしろ「ない」機能がいくつもある。でもファンにはそんなことは関係ない。デジタル商品も、また商品でもある
結局、何が変わろうが、人間の「より良く」「損はしたくない」という合理性と、「差別化したい」「よく見られたい」という虚栄心の織り目は変わらない。ただ織り込んでいる素材が速乾性でやたら伸縮性があるけど、なんか縫製が悪いのか肩や腰のあたりがフィットせずしっくりこない・・・そんな感じかな
Posted by 比嘉俊次 at 00:24│Comments(1)
│社会
この記事へのコメント
小学校などで行われる「食育」もアウトソーシングかな?
食事は家庭で、親がと言うわけにもいかなくっている?
食事は家庭で、親がと言うわけにもいかなくっている?
Posted by 比嘉俊次 at 2013年06月27日 18:41
at 2013年06月27日 18:41
 at 2013年06月27日 18:41
at 2013年06月27日 18:41










