2014年01月04日
スペイン史
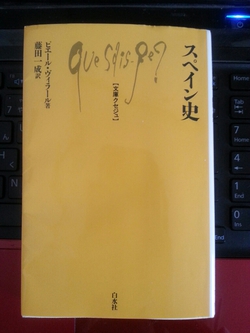
スペイン史
ピエール・ヴィラール 著
藤田一成 訳
白水社 文庫クセジュ731
スペイン通史はネットでもなかなか手ごろな本が見つからなかったが、ジュンク堂で発見。1992年第一刷、本書は09年の第九刷だがスペインが現体制になるまでが収録されている
まずスペインの哲学者・オルテガの著書から引用して、スペインには地理上の中心地を果たせる場所がなく「イベリア半島は無脊椎」としている。これは使い古された文句だそうだ
山脈が地域を分断している。ゆえにイベリア半島の歴史は「たいていの場合、中央部から表明される統合への意思と、やはり自発的な分立指向-それは地理的要因に根差している-との絶え間ない闘争だった」と第一章から切り込んでくる
中世~近世
永いモーロ人(ムーア人?)との戦い(781年間)の過程で各地域は自らがかちえた権利と戦いに対する誇り、そして近隣に対する不信感を抱くようになった
「スペインの実体が持つ新たな二面性~一方では自主独立路線~他方では超国家的な理想と情熱(カトリック信仰と守護)を求める傾向。この二つの傾向の間をスペイン人の意識は揺れ動いて容易に定まらない。これはいまだに続いている現象なのである」
「カスティリーヤ、レコンキスタ、そして中世などの精神―これらの精神は資本主義の萌芽に見られる事象に極度に逆行していた」
1580年にポルトガルとの統合(合同君主)が実現するも1640年にポルトガルは再度独立する(→ガリシア、イベリスモ)
「風土、人種、言語がカタルーニャを規定しているが、1750年から1830年の間、これらの要素はほとんど忘れられていた。~すなわち本当の問題は相違点にあるのではなく、特定の時期に特定の地域がこれらの相違点を再び意識するようになった理由の中になる。~かくしてカスティリーヤ人はカタルーニャ人に貪欲、金銭欲、威厳の欠如しか見いだせなかったし、カタルーニャ人はカスティリーヤ人に思い上がりと怠惰しか見出さなかった」
著者はフランス人だが、訳者によるとスペインでも名の知れたスペイン研究者だとか。スペインへの敬愛がにじみ出ているが、単なる「英雄史」にならずに宗教観や市民の感覚、生産基盤にまで言及した合理的な内容で理解しやすい。ただ、訳者が苦労したと言っているように、文章自体は詩的というか難解
訳者は神奈川外語大学の教授だがナバラ大学の修士課程を卒業し、数年間現地で研究生活を送っていたようでスペインへの敬愛の念を感じるいい翻訳だ
難しいが、164ページ、1050円(+税5%)では入門書として最適でお値打ち
近世~現代
1930年リベラ将軍の死によって共和制へ。「何かを変えなければならない、という考えはあらゆるスペイン人に受け入れられたようである。だが、なにを。共和国はやがて答えを出さねばならないだろう(所々こうした私的な表現がある。これは反語)」
「独裁政権は統治をしたが、変革をしなかった。共和国は変革を望んだが、統治することに難渋した」共和国の新憲法(1931年)はワイマール憲法をモデルに制定され、スペインは戦争の放棄を宣言し国際連盟に加盟。「改革を目指した急進的な共和国は、一般農民に直ちに満足を与えずとも、もっとも強力な労働者層に公然と敵対しても、スペインを改革できると考えていたために消滅した」
フランコ体制を経て新憲法制定にあったっての憲法論議では(1978年)国民のコンセンサスを得ることに不安があったため、スペインは「ゆるぎない統一に基礎を置く。が、さまざまな民族から構成されること、主権在民ではああるが国王は不可侵であること、そして自由な企業活動を保証するが経済の計画化を念頭に置くこと、などを宣言した」現実主義者は満足したが、国民に新体制への熱気はなく、36%が国民投票を棄権したという。
今日のスペインについては「往時の黄金世紀におけるように、きらびやかな豊かさと惨めな貧困が際立った対照を示しながらも併存している」としている
1930年リベラ将軍の死によって共和制へ。「何かを変えなければならない、という考えはあらゆるスペイン人に受け入れられたようである。だが、なにを。共和国はやがて答えを出さねばならないだろう(所々こうした私的な表現がある。これは反語)」
「独裁政権は統治をしたが、変革をしなかった。共和国は変革を望んだが、統治することに難渋した」共和国の新憲法(1931年)はワイマール憲法をモデルに制定され、スペインは戦争の放棄を宣言し国際連盟に加盟。「改革を目指した急進的な共和国は、一般農民に直ちに満足を与えずとも、もっとも強力な労働者層に公然と敵対しても、スペインを改革できると考えていたために消滅した」
フランコ体制を経て新憲法制定にあったっての憲法論議では(1978年)国民のコンセンサスを得ることに不安があったため、スペインは「ゆるぎない統一に基礎を置く。が、さまざまな民族から構成されること、主権在民ではああるが国王は不可侵であること、そして自由な企業活動を保証するが経済の計画化を念頭に置くこと、などを宣言した」現実主義者は満足したが、国民に新体制への熱気はなく、36%が国民投票を棄権したという。
今日のスペインについては「往時の黄金世紀におけるように、きらびやかな豊かさと惨めな貧困が際立った対照を示しながらも併存している」としている
Posted by 比嘉俊次 at 15:52│Comments(0)
│社会











