2015年07月12日
文字の歴史
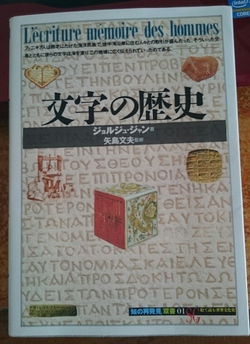 文字の歴史
文字の歴史ジョルジュ・ジャン
創元社
アルファベットを使うヨーロッパの文化の「文字の歴史」は概して面白くはないが、続けて「当り本」に遭遇
本書が面白いのはアルファベットの歴史は半分で、残りは「資料編」に読んだ記録を残す価値がある
この資料編は著者とは関係なしに、出版社がまとめたものらしいが、本文では散文的にしかあらわされていないアルファベットの歴史をチャート化したり、西洋人から見た漢字文化についてこちらの方が全然価値がある
中でも特筆すべきはイスラムの書家、ハッサン・マスーディの著書「書の美」からの長い引用だ・・・もしかしたら引用ではなくコラムか何かの転用かもしれない。そのくらいまとまりがあり、中身が濃い
まず驚いたのはイスラムにも「書」があること。文字の装飾に凝っているのは見ればわかるが、それは欧州のアルファベット文化圏の文字装飾とは違い、間違いなく「芸術」の域
偶像崇拝を許さないイスラム教の下で、文字によって精神性を表そうという取り組みが、ついには書を芸術の域まで高めようだ
道具を吟味し、精神を集中させて呼吸を整え白紙に向かう・・・「視覚も聴覚も無にならなければならない。内部の時間が外的な生活条件の制約を受けるようであってはならない」「規範は書家の内部のざわめきを鎮め、感情の氾濫を抑える役割をはたす。・・・基準体系は作品の評価のよりどころとなる。しかし書家はいったん確立された規範を越えなければならない」「白い紙の上の空間は・・・ただ黒い面と白い面があるだけである。そして黒の空間にも白の空間にもそれぞれ力がみなぎっていなければならない」「書の芸術には喜びも、幸福も、平和も、不安も、暴力も、すべてが込められている。これら様々な感情の動きを受け入れ、息吹を吹き込む書家の力量を通じて、その言葉はたとえ難解なアラビア文字で書かれていたとしても、普遍的な言語となる」「書家にとって表現とは、おそらく自由を実現する素晴らしい機会なのだ。言うべきことを大声で叫び、内心の心情を吐露するときなのであろう」「当時は斬新で豊かさを湛えていた古代の記念碑も、現代の我々には同じように伝わってこない。どの時代にもそれぞれのヴィジョンがあるのだ」
一つ一つの文字に成り立ちと意味がある漢字以外の文字文化圏で、文字自体がこれほどの高みに上るなんて。残念ながら日本で紹介されることが少ないイスラム文化の豊穣な世界をまた垣間見た思いだ。またこれだけの文化を表現できる日本語、翻訳者を揃えている日本もやはり素晴らしい
先日TVでも見たが、イスラム圏には日本でいう書道教室もあるようだ
Posted by 比嘉俊次 at 10:27│Comments(0)
│言葉













