2012年12月16日
漢字伝来
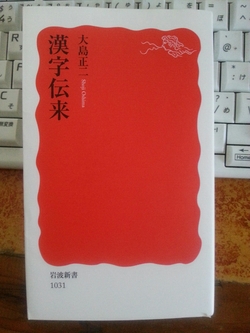
『漢字伝来』
大島正二
内容的には、高橋俊夫の「漢字と日本人」と重複する部分が多いが、こちらはより学術的
無文字社会だった日本に漢字が伝来して以降、これを日本語化する苦闘の歴史を振り返るもの
「漢字と日本人」よりも「漢字」に比重が置かれており、なるほど漢字が表意文字ではなく、「表語文字」である意味がよくわかる
漢字一つに中国語の言葉ひとつが対応する(もちろん言葉が増えた今はそうではない)という、「形・音・義→字形・発音・意味」が一体という今となっては珍しい文字。だからこれは単に「漢の文字=漢字」ではなく「漢語の文字」と理解すべき
当然、助詞が絶対的に必要な日本語では、「送りがな」が必要とされ、「宣命(勅令の読上げ)書き」などを経て、カナ(⇔真字)が生まれる
また、音節が少ない日本語で表せる「音」も少ないので、少々強引に中国語の音を落として、日本語にある音ではめ込んでいく
こうした下地があるからこそ、「!」や「?」を独自の解釈で取り込み、近年では「絵文字」を文中に取り込む事が出来るのかも。数年後には「?」と同じように絵文字も公式文書に登場か!?
西洋語も日本語の音節に落とし込む際のルールが何となく(?)確立できているし(「ヴ」だけは存続が微妙。足りない音節はいくつもあるのに、これだけ再現しようという意味がよくわからない)
しかしこの本で何と言っても面白いのは
周辺の文化圏の漢字への態度だ
元は、それ以前の征服王朝が漢化されたのを警戒し、チベットの高僧にパスパ文字を創作させた。が、結局はほとんど実用化されることが無かった
漢字をまねた部類では遼の契丹文字、金の女真文字、西夏文字。これらはいずれも国の消滅などにより現在では使用されていない
意外な道を進んだのはベトナムで漢字を借用して「チューノム」というい文字を作った。ベトナム語は中国語と同じく単音節で孤立語で相性もよかったはずだが、17世紀に渡来した宣教師によってローマ字の改良版が文字となった
また朝鮮族はいち早く漢字を取り入れたが、日本語同様、膠着語であるため漢字で言語を表すのは困難であり、ハングルが開発された。李朝四世王・世宗の治世下1443年と、常に中国の影響下にあったと思っていたが、これは意外と早く、しかも日本のカナのように、漢字を崩して取り出した文字ではなく、言語の音を分析した上で、開発された文字。だが漢字と中国えの遠慮から第二次世界大戦後まで、女性が使う文字として認識されていた
・・・等など。なるほど
気がつけば漢字を「国語」の一部としているのは、いまや日本だけではないか?しかし日本にしても漢字はかなり日本語化されている。例えば「合法的に入手」「合理的な判断」「時間的に無理」「平和的に解決」「徹底的に追求」などなどやたら使われる「的」。漢字だが助詞。英語的な表現でもあり、おそらく明治あたりに開発された使い方では?書き言葉からきていると思われ、口語にすると日本語の滑らかさが阻害されるが、前後の意味を簡単に接続できて便利。和語での言いかえがすぐには思いつかないぐらい日本語として定着している。さらに、逃げやあいまいさを残しているのが使いやすいポイント
また読みは日本語の発音に押し込められ、もちろん意味の連動はあるが、常用漢字に絞り込む過程でこれも単純化(→害と碍)されている。日本人は漢文を勉強しているので簡体字のコツさえつかめば、いくらかは意味を汲み取れる場合があるが、中国人は日本人が書いた文字で筆談するのは難しいだろう
漢字はもともと絵のような形から(象形)スタートし、抽象概念を表す言葉(指示)、それらを合わせて作られる(会意)、さらには偏の意味と旁(つくり)の読みからなる(形声)へと拡大し、当時の中国文化の先進性とともに周辺民族に影響を与えてきた
もちろん統治機構の確立・運営に文字は重要だったこともあるが、漢字に力があるのはそれだけではないはず
その字形の美しさと合理性、中国文化が生み出した抽象的な概念を表すと同時に文字そのものの様式美と、周辺国が受け入れ、反発しながらも漢字を無視できなかったのはわかる
興味深いのはその中国が他国の文化や文字を大量に輸入する番となった今、簡体字化を推進したぐらいで対応していけるのか、あるいはカナに行くのか
元は、それ以前の征服王朝が漢化されたのを警戒し、チベットの高僧にパスパ文字を創作させた。が、結局はほとんど実用化されることが無かった
漢字をまねた部類では遼の契丹文字、金の女真文字、西夏文字。これらはいずれも国の消滅などにより現在では使用されていない
意外な道を進んだのはベトナムで漢字を借用して「チューノム」というい文字を作った。ベトナム語は中国語と同じく単音節で孤立語で相性もよかったはずだが、17世紀に渡来した宣教師によってローマ字の改良版が文字となった
また朝鮮族はいち早く漢字を取り入れたが、日本語同様、膠着語であるため漢字で言語を表すのは困難であり、ハングルが開発された。李朝四世王・世宗の治世下1443年と、常に中国の影響下にあったと思っていたが、これは意外と早く、しかも日本のカナのように、漢字を崩して取り出した文字ではなく、言語の音を分析した上で、開発された文字。だが漢字と中国えの遠慮から第二次世界大戦後まで、女性が使う文字として認識されていた
・・・等など。なるほど
気がつけば漢字を「国語」の一部としているのは、いまや日本だけではないか?しかし日本にしても漢字はかなり日本語化されている。例えば「合法的に入手」「合理的な判断」「時間的に無理」「平和的に解決」「徹底的に追求」などなどやたら使われる「的」。漢字だが助詞。英語的な表現でもあり、おそらく明治あたりに開発された使い方では?書き言葉からきていると思われ、口語にすると日本語の滑らかさが阻害されるが、前後の意味を簡単に接続できて便利。和語での言いかえがすぐには思いつかないぐらい日本語として定着している。さらに、逃げやあいまいさを残しているのが使いやすいポイント
また読みは日本語の発音に押し込められ、もちろん意味の連動はあるが、常用漢字に絞り込む過程でこれも単純化(→害と碍)されている。日本人は漢文を勉強しているので簡体字のコツさえつかめば、いくらかは意味を汲み取れる場合があるが、中国人は日本人が書いた文字で筆談するのは難しいだろう
漢字はもともと絵のような形から(象形)スタートし、抽象概念を表す言葉(指示)、それらを合わせて作られる(会意)、さらには偏の意味と旁(つくり)の読みからなる(形声)へと拡大し、当時の中国文化の先進性とともに周辺民族に影響を与えてきた
もちろん統治機構の確立・運営に文字は重要だったこともあるが、漢字に力があるのはそれだけではないはず
その字形の美しさと合理性、中国文化が生み出した抽象的な概念を表すと同時に文字そのものの様式美と、周辺国が受け入れ、反発しながらも漢字を無視できなかったのはわかる
興味深いのはその中国が他国の文化や文字を大量に輸入する番となった今、簡体字化を推進したぐらいで対応していけるのか、あるいはカナに行くのか
Posted by 比嘉俊次 at 11:13│Comments(0)
│言葉













