2013年02月25日
沖縄の民衆意識
『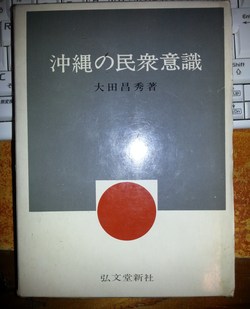 沖縄の民衆意識』
沖縄の民衆意識』
太田昌秀 弘文堂新社
昭和42年 750円 US$2.83
アマゾンで本を購入するも届かず。古本屋をのぞいてみるも欲しい本が無く、仕方なしに買った文庫本サイズの「ビジネス書」に後悔・・・時折人に勧めていながら、内容の詳細をほぼ忘れてしまっていた本書を十数年ぶりに読み返す
今時の本と比べると字は小さいし、所々漢字はインクの滲みでつぶれているし、いかにも50年前の学術書らしい味気なさで、そのくせ注が多くていったり来たりで、読むのにやたら時間がかかる
でも、やはり出色の出来
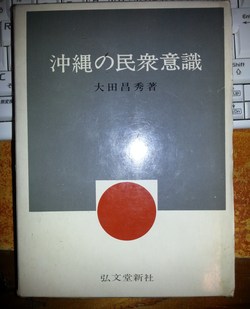 沖縄の民衆意識』
沖縄の民衆意識』太田昌秀 弘文堂新社
昭和42年 750円 US$2.83
アマゾンで本を購入するも届かず。古本屋をのぞいてみるも欲しい本が無く、仕方なしに買った文庫本サイズの「ビジネス書」に後悔・・・時折人に勧めていながら、内容の詳細をほぼ忘れてしまっていた本書を十数年ぶりに読み返す
今時の本と比べると字は小さいし、所々漢字はインクの滲みでつぶれているし、いかにも50年前の学術書らしい味気なさで、そのくせ注が多くていったり来たりで、読むのにやたら時間がかかる
でも、やはり出色の出来
廃藩置県に遅れること8年の明治12年の沖縄処分をもっても、その後続いた旧慣温存政策により「沖縄の民衆意識」は起動せず
謝花昇よりも先に明治26年、中村十作(本書では重作とし、諸説ありとしている)に率いられる形で宮古の農民がまず立ち上がる・・・などなど
著者はその後の様々な「事件」から、沖縄の中で絶えることの無い私的な対立や、事大主義に潜む劣等感や卑屈さ、そして沖縄に対する外部の人間の無知を沖縄の新聞の社説や沖縄について外部の人間が記した記述から列挙している
大田の言葉に力があった(今はかなりカドが取れた印象)のは、その舌鋒がウチナーンチュにも正しく向いているからだ。それは屋良朝苗と共通する部分
・・・というのは以前、読んだときに理解したこと
あれから普天間基地移設問題が、政権交代を経て「沖縄の問題」から全国の問題となり(でも今でも「沖縄問題」と括りたがる人がいる)、沖縄の中の対立や沖縄に対する認識が浮き彫りになってくると、同じ本を読んでも、また違った見え方、考え方が浮かんでくる
大田は本書で、軟弱な地盤(共有財産という経済基盤とそれゆえの自意識の薄さ)の上に、支えきれぬほどの急激な日本社会の変化(民主化)があり、それでは不安定になってしまうと沖縄特例で旧慣温存を図ったがために他県との差異がさらに拡大したことによる自他の意識の褶曲と、「追いつきたい」という焦りが生み出した圧力により、沖縄の民衆意識の特異な地層が形成されたことを見抜いている
具体的には・・・
定見の無い旧慣温存と見当違いの宣撫策による混乱の深化、人頭税から変わらない都市部と地方の意識の乖離・・という現代にも通じる基本的な構図の発見
さらには沖縄の視察団が文明開化路線を驀進する本土で好奇心にかられ繰り広げた珍道中(初めて見る汽車に「馬なき馬車!」と驚きの声をあげるなど)を面白おかしく書きたてた本土紙の記事に対しても怒りに筆を流されず「日本の紳士が欧米諸国で珍談の種をまきながら文明をもたらしたのと同じように、沖縄人も珍奇な経験を重ね、嘲笑、侮蔑も浴びながらも一歩一歩近代化への歩みを続けた」と冷静に受け流し、「しかし中には優れた洞察により核心にるれるものもあった」と、沖縄の病根を指摘する河東の紀行文などを紹介している
・・・50年も前にこう冷静に分析している大田の視点には驚かざるをえない。今日の論評はいかにもそれぞれの島のサイズに沿った狭量さで、(沖縄からしてみればとんでもないが)「南洋道構想」を打ち出した明治の大局観はない
これは大田の極端に振れた経歴(=鉄血勤皇隊と金門クラブ)が大いに影響しているだろう。そしてこの本が出版された後、沖縄の意識の地層はさらに複雑さを増している。例えば米軍治下であることを恐れず日の丸掲揚運動を率先していた教職員会を中心とする「革新」と、日本への復帰は時期尚早と高等弁務官の「芋と裸足論」を引用してまでしていた「保守」の入れ替わり。さらにその頃教育を受け「途中から日本人になった世代」とその前後の「再び日本人になった世代」と「生まれた時から日本人の世代」、さらに2000年あたりを境にした沖縄ブーム後の世代もあきらかに地層が違うような気がする・・・また幾たびかウチナーンチュは踏み絵を踏まされ、右に左に上に下に楔を打ち込まれているのもやっかいだ
しかし、やはり何と言っても大田世代、そして彼らに教育を受けた世代の意識は傍目にも複雑に見える。戦争という極限が試される中で赤誠(いまや死語か)を貫徹しながら、戦後は音もなく切り離され、呻吟して「復帰」を果たした彼らを迎えた「日本」の変わりよう・・・教育、意識、国力、アメリカの拡大、占領政策、世替わり等々、彼らの体験を慎重にトレースして想像すると暗い気持ちになる。やがて怒りに、そして失望に。自らの歴史を知らず、大局を見ずに時局に流されるだけで己の立ち位置すら解していない者とは相容れまい
佐藤も屋良も草葉の陰でさぞお嘆きだろう
50年前の学者の本らしく(大田はその頃助教授)、資料に沿った考察に徹した記述をしているため、最後も現在の本のようなわかりやすい「シメ」などは存在しない
ただ謝花昇の伝記を著した大里康永の言葉を引用し「参政権が実現した際、かつての「時期尚早論者」が真っ先に当選したくらいだから、それが沖縄に何の光明も与えなかったことは言うまでも無い。県制はしかれ、選挙法は施行されたが、県民の無自覚と事大思想の横行とは依然として沖縄の解放を未来へ押しやり、自由の保障を確保することが出来なかった」と結んでいる
意識や常識は親から子へ多くは無意識的に伝播してゆき、社会を作ってゆく。この本が世に出た後・・・復帰運動の盛り上がり~沖縄ブームまでの30年は価値観がまさに二転三転しておりその意識の地層を探る考察が求められているが、視点が一方的なものが多く、納得できる解説には未だお目にかかったことが無い
謝花昇よりも先に明治26年、中村十作(本書では重作とし、諸説ありとしている)に率いられる形で宮古の農民がまず立ち上がる・・・などなど
著者はその後の様々な「事件」から、沖縄の中で絶えることの無い私的な対立や、事大主義に潜む劣等感や卑屈さ、そして沖縄に対する外部の人間の無知を沖縄の新聞の社説や沖縄について外部の人間が記した記述から列挙している
大田の言葉に力があった(今はかなりカドが取れた印象)のは、その舌鋒がウチナーンチュにも正しく向いているからだ。それは屋良朝苗と共通する部分
・・・というのは以前、読んだときに理解したこと
あれから普天間基地移設問題が、政権交代を経て「沖縄の問題」から全国の問題となり(でも今でも「沖縄問題」と括りたがる人がいる)、沖縄の中の対立や沖縄に対する認識が浮き彫りになってくると、同じ本を読んでも、また違った見え方、考え方が浮かんでくる
大田は本書で、軟弱な地盤(共有財産という経済基盤とそれゆえの自意識の薄さ)の上に、支えきれぬほどの急激な日本社会の変化(民主化)があり、それでは不安定になってしまうと沖縄特例で旧慣温存を図ったがために他県との差異がさらに拡大したことによる自他の意識の褶曲と、「追いつきたい」という焦りが生み出した圧力により、沖縄の民衆意識の特異な地層が形成されたことを見抜いている
具体的には・・・
定見の無い旧慣温存と見当違いの宣撫策による混乱の深化、人頭税から変わらない都市部と地方の意識の乖離・・という現代にも通じる基本的な構図の発見
さらには沖縄の視察団が文明開化路線を驀進する本土で好奇心にかられ繰り広げた珍道中(初めて見る汽車に「馬なき馬車!」と驚きの声をあげるなど)を面白おかしく書きたてた本土紙の記事に対しても怒りに筆を流されず「日本の紳士が欧米諸国で珍談の種をまきながら文明をもたらしたのと同じように、沖縄人も珍奇な経験を重ね、嘲笑、侮蔑も浴びながらも一歩一歩近代化への歩みを続けた」と冷静に受け流し、「しかし中には優れた洞察により核心にるれるものもあった」と、沖縄の病根を指摘する河東の紀行文などを紹介している
・・・50年も前にこう冷静に分析している大田の視点には驚かざるをえない。今日の論評はいかにもそれぞれの島のサイズに沿った狭量さで、(沖縄からしてみればとんでもないが)「南洋道構想」を打ち出した明治の大局観はない
これは大田の極端に振れた経歴(=鉄血勤皇隊と金門クラブ)が大いに影響しているだろう。そしてこの本が出版された後、沖縄の意識の地層はさらに複雑さを増している。例えば米軍治下であることを恐れず日の丸掲揚運動を率先していた教職員会を中心とする「革新」と、日本への復帰は時期尚早と高等弁務官の「芋と裸足論」を引用してまでしていた「保守」の入れ替わり。さらにその頃教育を受け「途中から日本人になった世代」とその前後の「再び日本人になった世代」と「生まれた時から日本人の世代」、さらに2000年あたりを境にした沖縄ブーム後の世代もあきらかに地層が違うような気がする・・・また幾たびかウチナーンチュは踏み絵を踏まされ、右に左に上に下に楔を打ち込まれているのもやっかいだ
しかし、やはり何と言っても大田世代、そして彼らに教育を受けた世代の意識は傍目にも複雑に見える。戦争という極限が試される中で赤誠(いまや死語か)を貫徹しながら、戦後は音もなく切り離され、呻吟して「復帰」を果たした彼らを迎えた「日本」の変わりよう・・・教育、意識、国力、アメリカの拡大、占領政策、世替わり等々、彼らの体験を慎重にトレースして想像すると暗い気持ちになる。やがて怒りに、そして失望に。自らの歴史を知らず、大局を見ずに時局に流されるだけで己の立ち位置すら解していない者とは相容れまい
佐藤も屋良も草葉の陰でさぞお嘆きだろう
50年前の学者の本らしく(大田はその頃助教授)、資料に沿った考察に徹した記述をしているため、最後も現在の本のようなわかりやすい「シメ」などは存在しない
ただ謝花昇の伝記を著した大里康永の言葉を引用し「参政権が実現した際、かつての「時期尚早論者」が真っ先に当選したくらいだから、それが沖縄に何の光明も与えなかったことは言うまでも無い。県制はしかれ、選挙法は施行されたが、県民の無自覚と事大思想の横行とは依然として沖縄の解放を未来へ押しやり、自由の保障を確保することが出来なかった」と結んでいる
意識や常識は親から子へ多くは無意識的に伝播してゆき、社会を作ってゆく。この本が世に出た後・・・復帰運動の盛り上がり~沖縄ブームまでの30年は価値観がまさに二転三転しておりその意識の地層を探る考察が求められているが、視点が一方的なものが多く、納得できる解説には未だお目にかかったことが無い
Posted by 比嘉俊次 at 21:00│Comments(0)
│社会











